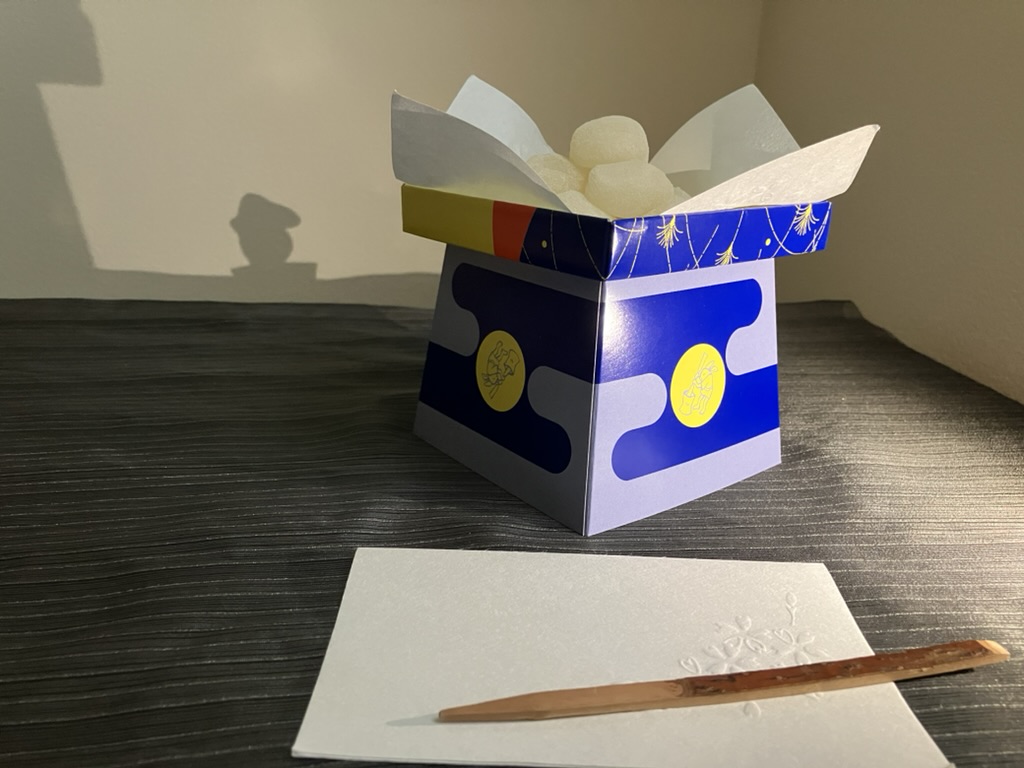秋の夜、空に浮かぶ美しい月。
古くから日本では、十五夜の日を特別に“お月見”として祝ってきました。
風習の由来
お月見は、中国から伝わった風習が日本に根づいたものといわれています。
十五夜は旧暦の8月15日、最も月が美しく見える日。
“満月のように円満に”という願いと、豊作を祈る意味が込められているそうです。
お供え物について
団子のほかに、すすきや秋の実り(里芋・栗・枝豆など)を一緒に供えることもあります。
すすきは稲穂の代わりで、魔除けの意味もあるのだとか。
自然に感謝する気持ちが、お月見の風習に込められているのですね。
実りの秋は、私たちにとって大切な季節。
近年はお米の価格上昇もあり、改めて「収穫のありがたさ」「食べられることの幸せ」を感じさせられます。
ただ、すすきを手に入れるのが難しくなってきているのも現代ならでは。
これまでのお月見は“楽しむ行事”という意識が強かったのですが、ここ最近は“感謝の心”を持つことの大切さを改めて感じています。
今年の十五夜は、感謝の気持ちを胸に、お月見を楽しみたいと思います。