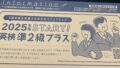うちの町内は20世帯くらいにもかかわらず、高齢化でひとり暮らしのお年寄りばかりです。50代のわたしでさえ若い人。シニアクラブも少ない人数だからと40代から自然と加入しておりました。そんな町内ですが、役員の負担と会長のなり手がいないため、脱退が出てきました。町内会が解散するとどうなるのかについて調べてみました。
町内会解散の問題点
- 地域のインフラや防災対策が手薄になる
- 防犯灯の維持、防犯パトロールが困難
- 防災訓練・避難所運営の減少 → 防災意識の低下
- 地域の支え合いが減る
- 高齢者や障がい者の見守り活動がなくなり、孤立が進む
- 住民間のつながりの希薄化
- 新しい住民が地域ルールを把握しづらくなる
- 自治体からの連絡や防犯情報を得る機会が減る
- 公共サービスの維持が難しくなる
- 自治体との交渉窓口がなくなり、地域の要望が伝わりにくくなる
- 町内会を通じた助成金が受けられない
- 道路補修や除雪などの対応が遅れる可能性がある
- 生活環境の悪化
- 地域の美化活動の停止により衛生環境が悪化
- 不法投棄や違法駐車が増加する恐れ
- ゴミ捨て場の管理ができず混乱を招く
高齢者の方の見守りは、子どもさんが遠方にいれば、すぐ関われるのは近所の方ですね。災害があったときでも近所ならすぐにかけつけられます。解散してしまっては、関わりの有無のみで限られた人のみに限定されてしまいます。顔見知りだからこそ、災害時はホッとすることもあると思います。
ゴミステーションはどうなる?
- ゴミステーションの使用許可が得られない
→ 自治体が町内会単位で利用を認めている場合、住民が使えなくなる→個人で - 不法投棄が増える
→ 誰が対応するのか問題になり、片付けの負担が個人にかかる - 粗大ゴミの回収が難しくなる
→ 町内会で集団回収をしていた場合、個別に依頼することになり費用が増える - ゴミ収集の契約が個人負担に
→ 町内会が自治体と契約していた場合、個々の世帯で対応する必要が出てくる
自治体による回収(平均的な金額)
【注意】料金は地域や業者によって異なり、回収量や作業内容によっても料金が変動する場合があるようです。
- 粗大ごみ
- 1品目につき300円〜3,000円程度
- 例:テーブル 300〜1,000円、タンス・食器棚 300〜2,500円、ベッド 1,000〜1,800円、ソファー 1,800円
- 自己搬入
- 1kgあたり15円〜100円程度
- 一定量まで無料の自治体もあり
民間業者による回収(平均的な金額)
- 定期回収
- 週1回:5,000円/月〜
- 週2回:7,000円/月〜
- 一時的な回収
- 粗大ごみ1点:500円〜10,000円
- 1部屋分:30,000円〜
- 一軒家全体:300,000円〜
- トラック単位の回収
- 軽トラック(2.5m³):55,000円〜
- 1トントラック(5m³):85,000円〜
- 2トントラック(14m³):180,000円〜
当たり前にゴミが捨てれると思ってましたが、これだけのコストがかかっていたのですね。本当に有難いことです。
できること
「ゆるい町内会」への移行
- 役職をなくし、無理なく参加できる仕組みを作る
- 必要最低限の活動(防災・防犯・清掃)に絞る
- 町内会活動の参加のハードルを下げる
- 役割を細分化し、短期間・少人数で負担を分散
結論
町内会が解散したとしても、ゴミ問題の管理は継続が必要です。では、それを誰がどのようにまとめるのかが課題となります。そのため、町内会を維持しつつ、より柔軟な「ゆるい町内会」へ移行するのが良いのではないでしょうか。
町内会の年齢層は幅広く、それぞれの考え方に違いがあります。これまでのやり方を大切にしたいという意見も理解できますが、時代に合った方向へと転換しなければ、維持が難しくなってきています。
防犯の面では、町内の顔見知りの関係があるからこそ、見知らぬ人に注意を払ったり、異変があれば教えてくれたりします。地域のつながりがあることで、防犯対策にもつながるのです。
また、町内で計画されていた企画が住民の反対により白紙になったことがありました。これは、町内の意見がしっかりと反映された良い例だと思います。この時、すぐ近くのマンションには案内が出されていませんでした。それを考えると必要だとも思うのです。
町内会を完全に解散すると、地域の安全や生活環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。現代のライフスタイルに合った形で最低限の機能を維持しながら、住民の負担を減らすことができれば理想的だと思います。